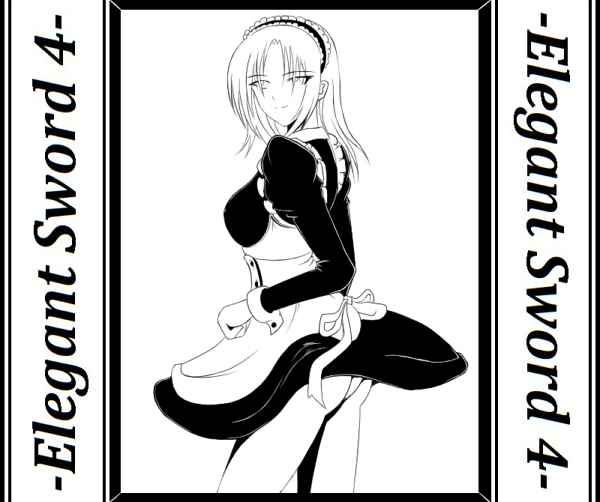
パン・アルバード 2
ニューヨーク市民のダニエル(42歳)は、事件が起きた時の状況をこう語った。
「人はすごく多かったですね。野次馬と取材の記者たちが。なんたってニューヨーク市警が治安強化の切り札として導入したロボット『ED-2009』のお披露目でしたから、はい。私も家が近かったから見物に来てたんです」
その日はニューヨーク市民にとって特別な日だった。アムステラ帝国が地球に襲来してすでに長い月日が経ち、一方ではその異星人たちに迎合する『ブラック・クロス』ら凶悪なテロ組織の脅威に晒され続けるアメリカ。各地の治安は悪化の一途を辿り、早急な対策が求められていた。
事態に着目したコングロマリット企業のO社は、多額の研究費を投じて警備ロボット『ED-2009』を完成させた。コンピューターが犯人を自動で認識し、独力で排除・無力化する最先端技術の結晶である。嘘のように聞こえるが実用化にこぎつけたのだ。
「お披露目が架橋に入った時、そのEDがみんなの前に運び込まれました。すごいなって思いましたね。それから、女優の誰でしたっけ、とにかく女性が警察署長と一緒に起動ボタンを押したんです」
悲劇は突然だった。動き出したED-2009は合成音声で語りだす。
『犯人を発見。制圧します』
署長が顔にしわを寄せながら、「早速仕事を始めた」と喜んでいた。
『銃を捨てて投降しなさい。さもなくば発砲します。繰り返す……』
ED-2009の両手に備え付けられた大口径機関銃が署長に向けられた。
「その頃にはみんな、何か変だって思い始めましたね。それからすぐ、署長が撃たれたんです、こうババババババババって」
鉛の洗礼を浴びた警察署長は細切れの肉塊と化した。一瞬の静寂を挟み、辺りは悲鳴に包まれた。
『犯人が抵抗を続ける模様。制圧の許可を。せいせ、セイセイセイシけhがぢ』
暴走した。
ED-2009の機関銃が観衆に向け乱射され、ダニエルはその中を必死になって逃げた。だが周りの人々も我先にと逃げ出し混乱が極まる。
「もう前も後ろも分からなくって、僕も死ぬかと思いました。そしたら一人男がEDに近づいていって……」
ダニエルはその光景を説明するために記憶を租借し始めた。
「……まだ信じられないんです。あの時に起きたことが」
男は、群集を掻き分けてED-2009に近づいた。その歩行はゆらゆらとしたもので、とても危機感など無い。
EDが気づいた。最早、音声は声の形を成さず、雑音と機械音を唸らせながら銃を向けた。ふと、男の姿が消える。ダニエルの目にもそう見えた。
一足飛びで側面に回った男がそこにいた。次の瞬間、蹴りを見舞う。すると1tは超えようかというEDの体がひっくり返ったのだ。EDも、観衆も、何が起きたのか分からない。
EDは必死になって相手を探していた。ギシギシと音を鳴らしながら起き上がると、男に再び銃を向ける。発砲。もうそこにはいない。男は10mほど飛びのいていた。
そこで気づく。背後に人がいた。EDがやたらと撃てば流れ弾で怪我人が出る。だが男は慌てた様子も無く、傍にあった道路標識を引き抜いた。3mはあるその標識をぐるぐると振り回して、EDの銃撃を軽々と叩き落し始めた……!
「そこからは私が話そう」
ED-2009の開発に関わった科学者グーテ氏が引き取って説明を始めた。
「ED-2009の機関銃は分厚い鉄板を軽く撃ち抜けるほどの威力があります。それに対して道路標識ですが、まずあれは棒じゃありません。金属の板をつないだ筒状の物でした。普通に弾が当たれば標識はバラバラになるところですが、そうはならなかった。これが意味するのは、あの男が標識を使って、当てるのではなく掠らせた、軌道を逸らしたんですよ。高速で移動する弾丸に僅かな力を加えるだけで、的確に、安全な方角へ流す。弾丸を視認するだけでも異常なことなのに、神業です」
人間の力に科学力が敗れたという事実にグーテ氏は悔しそうだった。
EDは銃弾を撃ちつくし、わずかな間、再装填のために動きが止まった。それを見て取ると、男はEDの懐に駆け込み、次いで飛び上がった。標識を高々と掲げて、EDの体に突き刺す。EDはその場に崩れ落ちた。
わずかな間に行われた攻防を、人々は見守っていた。そして、それが終わると、打たれたように歓声を挙げた。
ダニエルもこの幻のような劇的事件に、何が現実か判断がつかないほど躍り上がった。謎の男に駆け寄るとその手を取り、単純な疑問をぶつけた。
「あんたは一体何者なんだ!?」
「アムステラの焔伯と申す者だ」
「は? あー、あむ?」
「遠き異星のアムステラから来た焔伯だ、と言った」
パン・アルバードは奔走していた。
地球の特機との戦いを控え、その準備に追われる中、突然ブラック・クロスから抗議を受けたのだ。「あなたの師匠が、ブラック・クロスの細工したロボットを破壊したのだ」と言われた時、パンは天地がひっくり返るかというほどの衝撃を受け、しばらく言葉も出なかった。
その場は謝るだけ謝って、事態が明確になってくると再び謝罪。今は、軍が焔伯と接触し、パンの元まで連れてくることになっていた。
アムステラに12人しかいない武の化身『快王』。焔伯もその一人だが、『焔伯』とは本名ではない。パンの師匠である焔伯は、名をホウシュンと言い、『アムステラ鍔家流』の師範として、アムステラの数百万人の門下を束ねる立場にある。鍔家流とは『アムステラ静心流』の分派の一つで、一個の勢力を成しており、歴代の師範は称号を名乗ることが慣例となっている。
フランダル家はこの鍔家流と長年関係を持っており、パンもその縁で修行に赴いたのだ。
その師範が、輸送ヘリに乗せられて現れた。
「ようようパン、元気にしてたか?」
「師匠……」
開口一番、パンは上段回し蹴りを見舞った。焔伯は、笑みを浮かべたまま簡単にそれを避ける。
「こんな所で何をしているのですかあなたは!?」
「訛ってはいないな。だが上達してもいない」
「師匠!」
「お元気でしたか!」
パンと同じく門下生である八旗兵たちが恩師との再会に沸き立った。
焔伯は奇妙なヘルメット軍団に面食らっていた。
「何だその格好は?」
「これですか」
談話室で焔伯が尋ねた。八旗兵は、フランダルに仕えてから、顔を覆うヘルメットに揃いの胴着で身を固めている。傍目には異様な集団だ。
「よくぞ聞いてくださいました。SPというものが居りますが、彼らはみな、似たような角刈りにし、黒のスーツで服装を統一することで、それぞれの差を無くし、個人を特定しにくくすることでSP自身の危険を避けているのです。それに習って」
「ふーん、そうなのか……」
「それで師匠」
イライラしながらパンが会話を断ち切る。
「何故師匠がこの星にいるのですか!?」
「暇だから」
「……」
思わずうな垂れる。
「お前たちが勝手に出て行ってから、残ったのは青二才ばかり。指導してもつまらんから、師範代たちに任せてきた」
「フフッ、師匠も寂しがり屋ですなあ」
「まったくまったく」
「サボっていないか見に来ただけだ、バカモノども」
「それはいいですから……師匠。どうして連絡の一つもくれなかったのですか?」
「うむ、バレたらお前たちが手回しして出国停止されるから」
困ったものだ、と言いたげに手をヒラヒラとさせる焔伯。予想していた答えとは言え、パンは呆れざるを得ない。
「当たり前です。誰かが側にいないと薬も飲まないお人ですから。腰の具合はあれからどうなのですか?」
「ああ、うむ。このとおりホラ」
言いながら焔伯は視線を逸らした。
「目を見て話してください師匠。肩、膝、腰に爆弾抱えているのに無理しないでください」
「人を老人扱いしおって……」
「何か?」
「何でもない……」
焔伯は40半ばにして、すでに体の内外至る所を病んでいた。若いころの激しい修行が、彼の衰えを他人より早いものとしている。
そのいくつかはアムステラの高度な医療技術を用いれば改善可能だが、焔伯は体にメスを入れることを拒んだ。
「まあいいです、来てしまったものは仕方がありません。それで今回の騒ぎは何なのですか? ブラック・クロスの工作を妨害したそうですが」
「内緒で来たはいいが、お前たちの居場所が分からなくてなあ。何か騒ぎを起こせば、そっちから接触してくると思って。しかしそういう裏事情があったとはな、すまんすまん。
まあ気にするな。地球人でありながら、他国の侵略に手を貸す連中のやることなんか、気にかけてやることもあるまい」
「そういう問題では……はぁ、いいです」
こんな男だが、若いころは生死をさ迷うほどの難行苦行を自らに課し、多くの激闘を経てきた彼を『燃える男』とか、『炎の快王』と称する人々もいるのだ。
今では病院通いの快王だが。骨や靭帯を断つ大怪我を何度も経験し、内臓にも持病を抱えていて朝昼晩の薬を医者に渡されている。それでいて日々の鍛錬をやめないので慢性的な痛みが消えることは無い。
「まあいいです。実を言うと相談したいことがあったので手間が省けました」
急に深長な面持ちになると、パンは焔伯の前に膝を揃えて座りなおした。
「師匠、私は今一度、自分を鍛えなおしたいのです」
「何だと?」
パンはエドと共に戦う内に、自分の力量が足りないのではないかと考え始めていた。先日の勝利も、参謀に加わったネスターの知恵によるところが大きい。
「地球で戦うために修行をほっぽり出しておいて、今度は修行させてくれ、と来たか。勝手なことだな」
「それは分かっています。ですが、私はもっと力をつけなければいけないのです」
「ランカスターとかいう男爵殿のことはいいのか?」
「……」
このことはまだエドに了解を取っていない。順序が逆なことも分かっていたが、エドには話せないでいた。
「しかしなあ。今以上に強くなろうとすれば相応の訓練が要るぞ。俺は女のお前にそこまでやらせたくは無い、正直言って」
「女であろうと武に生きる者です」
「ダメなこともある。体が大きくないお前は他人より無理をしないとならぬ。それが後々になって人生を蝕むこととなる。俺がいい例だ。……例外もいるが」
最後の言葉だけ、苦虫を噛み潰したような顔で言った。それを見てパンは、その原因となっているであろう人物を何人か思い出した。
アムステラで武を志す者の中には、多くの女傑たちがいる。その一人としてまず挙げるならば、帝国の第一皇女ヒルデガード・アムステラだろう。彼女は若干12歳で快王の位を持つほどで、多少なりと形式的意味もあろうが、すでに大人顔負けの実力を持っている。
次に、ギャラン・ハイドラゴンの娘、ルルミー。徒手空拳による操兵戦闘術の先駆けとも言えるギャランをして、『自分を超える逸材』と言わしめたほどの才女だ。多少(?)荒削りなところもあるが、地球の戦場においても勇名を轟かせている。
そしてもう一人。12人の快王に名を連ねるヴァーリス・ミナ・アージェントという女がいた。エリュシオンという星に伝わる『彩刃流気功術』を操る彼女は、今や生きているのかすら分からないベールに包まれた女性だ。ただでさえ他星出身の彼女は、10年ほど前に行方不明となっており、その人物像と流派は 伝 説 の 域 に達するのではなかろうか。
このヴァーリスと焔伯は面識がある。パンは体格の近い彼女をひそかに目標の一人としていたため、焔伯の知る彼女のことを聞きたがった。だが焔伯は忌々しそうに、口をへの字に曲げるだけだった。
どうも過去に負けたことがあるらしい。才能のある人間に嫉妬するのが彼の悪癖だった。
ふと、ドアが開き、エドが現れた。
「パンこのメイド服着てみてくれ。……ん」
エドの視界に見慣れない中年男が、顔を顰めて佇んでいる。それでエドは、パンたちの師匠が地球に来ているという話を思い出した。
「あんたが鍔家流の快王か。俺様がエドウィン・ランカスターだ、よろしくな」
「うむ……」
エドの差し出した手を握りながら、目で測るように焔伯はエドを見る。
「はるばるこんな星に用でも? 八旗兵たちに会いに来たのか?」
「会いに来た、というかなあ……。そうだな、連れ戻しに来たってところか」
「連れ戻す……?」
エドの表情が曇る。
「八旗兵たちは大事な部下なんだが」
「主の部下である前に俺の弟子だ。今の中途半端な腕で人前に晒すのは気が進まん」
「おいおい勝手言ってくれるなよ。パン、どうなってんだ?」
エドがパンに説明を求めたが、パンは俯いて何も言わない。そのことがエドを焦らせた。
「待て、待てよパン……。お前がいてくれないと、ちょっと困るんだ。何とか言えよ」
「私は……お役に立てているでしょうか?」
「役に立つも何も、いてくれないとあれだ、う〜んとだな」
「やめておけパン。聞けば、この男はボンクラ男爵として有名だそうじゃないか。そんな奴に忠を尽くしたところで何になる?」
「あぁん?」
エドが怒る。パンもこの焔伯の言い方にはムッと来た。
「お互い武門に生きる男だ、話して解決することもない」
「……」
「どうだ男爵、俺と戦ってみるか?」
「……何!?」
「俺に勝つことができたら、パンたちをこれからも地球で戦わせてやる」
焔伯の意図にパンは気づいた。敢えてエドを挑発しているのだ。そしてこれを受けたエドがどういう反応を示すかも何となく分かり、止めるべきかと思ったが。
「言ったなオッサン。その言葉忘れるなよ、勝負だ!」
「いいぜ小僧。お前ら、椅子とか片付けろ。ここでやる」
「ほ、本当にやるのですか!?」
驚いた八旗兵はパンの顔色を伺った。止めるべきだ。しかし、パンは動かなかった。彼が、エドが戦う。それも自分のために。見たい。見ていたい。
軽く準備運動をした後、戦いは始まった。両者とも上着を脱ぎ捨て、正面から 相 対 す 。
軽快に左右へステップを踏んだ後、エドは身構えた。
勝てるわけが無い。エドの身体能力は中々のものだが、相手は武の最高峰が一人・快王焔伯である。
それでもエドは戦おうとしていた。
「パン様、よろしいのですか?」
「……いいんだ。何より師匠自身がエド様を知りたがっている」
そして自分も戦いの行方を見守りたい。
先に動いたのはエドだった。両腕をするりと下げ、直立したまま堂々と間合いを詰める。
(エド様、それは無謀な……!?)
「ほほう……」
焔伯は、軽薄そうな青年の第一印象を若干改めた。一見ただ歩いているだけに見えるエドだが、これぞアムステラ貴族に伝わる『執事流歩法術』だった!
執事流歩法術とは、正中線を崩さず体の安定を保ち、いかなる方角の変化にも即対応できるようにする執事必修の歩行術である。この場合、注意しなければならないのは、堂々と音を立てながら歩くことで、主人に自分の居る位置をアピールし、決して驚かすようなことがあってはならないということだ。実用的でありながら執事の分を忘れない、なんともエレガントな歩行術である。
本来これは貴族の学ぶ物ではない。だがエドにとっての戦いの師は物静かな執事であり、彼を追ううちに自然と身についたのだった。
(単なるボンボンでは無いようだな。だがしかし)
この歩行術は守りに適したもので、こちらから攻めなければ脅威ではない。間合いが詰まっても焔伯は動かず、ひたすらエドが仕掛けてくるのを待った。
瞬間、エドの両腕が唸りを上げる。攻撃はボクシングスタイル、素早いジャブの連打。それを焔伯は両腕で正確にブロックした。逆に打ったエドが手を痛めるほど、それは素早い動作だった。
それでもエドはラッシュを続けると、焔伯は掌で、甲で、軽く受け流した。
「出た、焔伯様の“流水把”!!」
鍔家流が得意とする防御の型、“流水把”。両手を前に軽く構えた体勢から繰り出される、わずかな攻防の間に敵の呼吸、力の流れ、打ち込みの角度や癖を読み取り、最低限の力でも攻撃を受け流せるようになる防御法のことだ。
熟達したものならば矢玉であろうと受け流せると言う。焔伯にしてみればこの程度の打撃は止まって見える。
正面突破は叶わないと悟ったエドは、素早くバックステップして距離を取ろうとしたが、その動きは読まれていた。コンマ単位の誤差で焔伯も前進し、肉迫すると、エドの腹に深々と肘を打ち込む。
「 げ ぼ ぉ っ !! 」
エドにとってこれほど強く殴られるのはめったに無いこと。思い切り嘔吐しながら、それでもダウンはしなかった。
回復も待たずにエドは進む。正面がダメならばと、左右にステップを踏みながら勝機を伺う。焔伯は直立不動。またもエドの攻撃を待ち構えていた。
堪え性も無くエドはストレートを放つ。これを焔伯は、肘で跳ね返し、その反動でエドは体勢を崩された。
倒れまい。エドが足を踏み締める。とっ、焔伯が軸足を払った。咄嗟に手を付いたエドだが、その手を焔伯は容赦無く踏みつけた。
そして蹴る。180cmあるエドの体が宙に浮き、壁に叩き付けられた。
「子供扱いだ……」
八旗兵は焔伯が軽くあしらう程度と思っていたが、ここまで力を出すとは考えていなかった。敵が動かざるを得ない状況を作り、行動を、判断を束縛する。ああすれば、こうする。武術とは兵法であり、兵法とは他者に勝って生き残る術だ。敵の動きに合わせどう対応するか、数え切れないシミュレートを彼ら武術家は実践してきた。数多くの戦いを経てきた焔伯に至っては100手先まで予測が行き渡る。
(まるで水を相手にしてるように、力が通じないじゃねえか……!)
やられながらもエドは状況を把握しようとしていた。
鍔家流はアムステラ静心流の分派の一つ。人の持つ力より、相手の力、武器の力、地勢、心理を突き詰めて勝利を掴む、弱者の兵法。
その総帥の地位にある焔伯は、テッシンや快王ハックルなどの剛拳使いとは対極に位置する、技巧派、柔拳の快王なのだ。戦法は受けを基本とし、いかなる力も受け流す。エド程度の膂力では肩慣らしにしかなるまい。
その上、彼は他の快王の流派を研究することも欠かさない。快王の地位にある武術家には、謎の気功術や岩石の如き鋼体を創る者、果ては毒使いや、武術家ですらない者もいる。それに比べて拳闘のなんと分かりやすいことか。
エドの蹴り。これもブロッキングで相手の体勢を崩し、返す刃、砕こうかというほどの威力を込めたミドルキックで、エドの左腕を破壊しかけた。
だがそれでも
エドの戦意は衰えていなかった。
「パンは連れて行かせねえぞ……!」
眼光鋭く焔伯を睨む。その面構えは歴戦のつわものたちと遜色無い、『男』のものだった。
(……そんな眼で見られちまったら)
全力で打ち込むしかない。今まで確固たる意志を持ち立ちはだかった者たちは、例え弱くても、格下でも、けして手を抜くことは無かった。
「ぐおおおおおおっ!」
がむしゃらに突き出されたエドの拳。
今度は防がない。焔伯はエドの懐に一瞬で飛び込み顎へかちあげ式の掌打。
エドの加速を逆用してのカウンターは脳を揺さぶるだけに終わらず、顔を掴み、床に叩きつける!
意識を朦朧とさせたエドは、後頭部に柔らかい感触を受け、そのまま眠りに落ち込んだ。
「男同士の勝負に割り込むとは何を考えている」
「申し訳ありません……」
眼に涙を浮かべつつ謝るパンは、自分の胸を枕にエドを抱え込んでいる。最後の叩きつけは彼女の介入によって不発に終わった。
あの気分屋が自分のために強大な相手と戦った、それが嬉しくて、それだけで充分だった。
「半端者が。まずは戦うということがどういうことか、その男の下でしばらく学ぶがいい」
「……そうしようと思います師匠」
「まあ人生長いんだ。答えを出すことに焦る必要は無い」
エドウィン・ランカスター、肋骨、左腕、亀裂骨折。打撲10箇所以上。歯を3本欠損。入院。
焔伯はその後、ランカスター隊に居付いてしまった。
<続く>